物の数え方に見る日本の文化 「ビーバップ!ハイヒール」より

竹島プロジェクト2011にぜひご参加を!参加方法はこちら。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日から通常国会スタート!
……でも、特に書くことがありません(T^T)
だって菅さんの演説聞いても、なーんも心に響かない。
「与野党協議のお願い」以外は、ほとんど印象に残りませんでした。
ま、今さらこの人に期待することなんかひとつもないんですけどね(てか、最初からひとつも期待してない(^^ゞ)。
というわけで、今日はこの番組をご紹介。
 ■1/20放送「ビーバップ!ハイヒール」〜数え方のミステリー〜
■1/20放送「ビーバップ!ハイヒール」〜数え方のミステリー〜木曜深夜11時台の放送にもかかわらず、二桁の視聴率をとるという関西の人気番組です。
この日のテーマは日本語の助数詞、すなわち物の数え方について。
これって私たち日本人にとっても難しいんですよね〜。全部言えます!なんて人はおそらく一人もいないでしょう。
例によって、番組の中身をざっくりとですがまとめてみました。
【番組公式サイトより】
数え方のミステリー モノの数え方にはワケがある
タンスは1台ではなく1棹!モノの数え方には意味や由来がある!サルは一匹、ゾウは一頭!“匹”と“頭”の違いとは? 番外編!?浮気は“三度目”より“三回目”が罪深い理由とは?
「ハテナの自由研究」は、ブラックマヨネーズの「女のウソは見抜けるか?」。
【出演者】
ハイヒール(リンゴ・モモコ)
筒井康隆、江川達也、たむらけんじ
ブラックマヨネーズ(小杉・吉田)、宮崎麗香
町田健(名古屋大学大学院文学研究科教授。東京大学文学部助手、北海道大学助教授などを経て現職。著書に「言語学が好きになる本」「間違いだらけの日本語文法」「町田教授の英語の仕組みがわかる言語学講義」「ソシュール入門 コトバの謎解き」など多数)
※一部進行を変えて再構成しています。
※「ハテナの自由研究」コーナーはカットしました。
大ざっぱな内容紹介ここから_________________________
■プロローグ
次のモノの正しい数え方と由来を知っていますか?
●ウサギ
一羽、二羽……。
昔、四つ足の獣を食べることのできない僧侶が、「ウサギ」を「鳥」にこじつけて食べたから。
●イカ
一杯、二杯……。
胴体をひっくり返すと、形がまるで入れ物のようだから。
●タンス
一棹、二棹……。
タンスを運ぶ時、棹にかけて運んだのが由来。
●思い出の写真
一葉、二葉……。
葉とは木の葉のこと。昔の日本人には舞い落ちる木の葉を愛でる感性があった。だから思い出の写真や大切な葉書などは、木の葉に喩えて数える。
世界中で日本ほどモノの数え方の豊かな国はない。
数え方がモノによって違うのは一見面倒くさいが、なぜそう数えるのか、その意味を知れば、きっと誰もが日本の文化を好きになる。
町田健氏、曰く。
「物の数え方には必ず意味がある。そしてその意味を知れば、身の回りにある何気ない物の一つひとつに、実に色んな歴史や文化があることが分かって、毎日を豊かに暮らすことができるでしょう」
「いろんな自然現象とか物に区別をつけて、名前を付けるというのが日本人は好き。他の民族にもあるが、日本人は特にやっぱり自然界とかに関心が強いから。日本語の助数詞の種類は、外来語も含めれば800以上ある」
「同じ物でも数え方が変化する。魚は海で泳いでる時は『匹』、尻尾が付いてるから売る時には『尾』、おろしたら『枚』、切ったら『切』…というふうに、物の形状や見方によって変わる」
■生き物の数え方
猿やリスは「一匹、2匹…」、象やキリンは「一頭、二頭…」。
「匹」と「頭」の違いは?
大きいのは「頭」と数えるようだが、その理由は?
そもそも「匹」とは?
もともと日本人は大きい動物も小さい動物も「一匹、二匹…」と数えていた。
「匹」という漢字、これは馬の尻の形を表しているもの。
昔の人にとって、最も身近な動物が馬だった。
馬を数える時の「匹」を、他の動物にも使うのは自然な流れだったのだ。
しかし、馬は現在「頭」と数える。なぜ?
もともと馬も「匹」で数えていたのに……。
実は、大きな動物を「頭」で数えるようになったのは、明治時代の終わり頃。
英語の数え方の影響を受けたから。
欧米では牧場の牛を数える時、牛の頭の数を数えていた。
この時、使う単位が「ヘッド(head=頭)」。
そこで、牛以外でも、ある程度の大きな動物は、数を「ヘッド」で表すのが一般的なのだ。
明治の終わり、この「ヘッド」を、「頭(あたま)」つまり「頭(とう)」と直訳したため、いつしか大型の動物は「頭」と数え、小型の動物は今までどおり「匹」で数えることになった。
では「頭」と「匹」の境目は?
それはやはり人間が基準。
人間より大きいものは「頭」、小さいものは「匹」と数えるのが原則。
■機械の数え方
電化製品を思い起こすと、冷蔵庫、洗濯機、テレビなどはそれぞれ「一台、二台…」と数える。
台にしているわけでもないのに、なぜ「台」なのか?
もともと日本人は昔から、物を乗せる台だけを「一台、二台…」と数えていた。
鏡台やちゃぶ台、秤(はかり)など、何か物を乗せる物だけを「台」で数えていた。
それが荷車や牛車、人力車など、車輪が付いている物も、人や物を乗せる物なので「台」となった。
ところが明治の終わり、機械に対しても「台」を使う数え方が一気に広まった。
一体何があったのか?
それは文明開化。
日本人の生活に怒濤のように押し寄せた西洋文化の波。
中でも一番のインパクトだったのが、自動車の出現。
当時の人々は、機械といえば、まず自動車を思い浮かべるようになった。
それほど自動車は、強烈な印象を与える機械だったのだ。
そして自動車は人を乗せるので、「一台、二台…」と数えた。
自動車は、この時代の人々にとって機械の代表。
だから日本人は、いつしか自動車以外の機械全般を「一台、二台…」と数えるようになったのだ。
では、ロボット犬の「アイボ」はどう数える?
これは「一匹、二匹…」。
1999年、日本で犬型のペットロボが初めて売り出された時、メーカーは「一台、二台…」あるいは「一点、二点…」と数えていた。
ところがこのペットロボがあまりに精巧で本物らしかったため、人々は情が移り、これをペットに対する「一匹、二匹…」という数え方に変わっていった。
このように、物の数え方は時代によって変化する。
近い将来、人型ロボットが進化し人間に近づけば、「一台」ではなく「一人」と呼ばれるようになるかもしれない。
■数え方を変えることで「デコレーション」?!
広告などを見ると、よくこういう表現をしている。
豪華に感じさせることができるから。
・新築住宅3戸分譲 → 新築住宅3邸分譲
・幕の内弁当1個 → 幕の内弁当1折り
・みずみずしいリンゴ1個 → みずみずしいリンゴ1玉
■食べ物のおもしろい数え方
握り寿司は二個で「一貫」と数えるが、なぜか?
そこには江戸時代のお金事情が隠されている。
「貫」とは江戸時代のお金の単位。
握り寿司の屋台で出される寿司の大きさが、ちょうどヒモを通した穴あき銭を束ねる時の大きさとほぼ同じだったので、「貫」で数えるようになった。
しかし、この握り寿司はかなり大きかったため、後に、食べやすいようネタとシャリを半分に分けて、二個握るようになった。
これが、にぎり寿司二個で一貫という数え方の始まり。
但し、回転寿司では通用しない。一皿、二皿と数えるから……(笑)。
次にラーメンについて。
ラーメンの数え方は正しくは「一杯、二杯…」だが、ラーメン屋さんで注文すると、お店の人は「ラーメン一丁!」といった言い方をする。
そこには店側の事情があった。
なぜなら、「丁」の方が景気づけになるから。
もともと「丁」という漢字には、物事が盛んな様子を表す意味がある。
たとえば、「一丁、挑戦してみるか!」とか「ふんどし一丁」のように、威勢のいい印象を与えるようによく使われる字。
だからラーメン店のような大衆的な店では、店を盛り上げるために、あえて店員が「ラーメン一丁!」と叫ぶのだ。
■「回」と「度」の違いは?!
「三回目の浮気」と「三度目の浮気」ではどう違う?
実は「回」と「度」では全然意味が違う。
「度」は、「二度目の優勝」や「一度だけ見た」というように、その後に同じことが繰り返されることが確実でなかったり、予測しにくい場合に使われる。
「回」は、「三回忌」や「第63回大会」など、繰り返されることがほぼ確実な場合に使われる。
したがって、
「三度目の浮気」=また浮気するかはわからない
「三回目の浮気」=ほぼ確実にまた浮気する
となり、「三回目の浮気」の方がより罪深いのだ。
「度」「回」の違いは、それぞれの漢字の成り立ちや意味を考えるとわかる。
「度」はもともと物差しのこと。物差しは永遠に長くすることはできない。つまり次に起きるかどうかわからない時に使う。
一方、「回」はぐるぐる回っていることを表す文字。何度も起こるぞということ。
■その他いろんな物の数え方
クイズです。次の物の数え方(助数詞)は何でしょう?
解答は下の方にあります。
・ぶどう
・花
・明太子
・イス
・テント
・電車
・プール
・ピラミッド
・ヒラメ
・蝶
・神様
・入れ歯
_________________________大ざっぱな内容紹介ここまで
「数え方を変えることで『デコレーション』する」というの、確かによくやってますね。
私はチラシ版下作成の仕事をしてるので、よくわかります(^^ゞ
特にリンゴとか梨とか、「個」より「玉」を使うスーパーさんの方が多いです。
ちなみに、キャベツや白菜は1個(1玉)でなくカットして売られる場合も多いんですが、その場合は「1/2カット」(2分の1カット)というふうに表現することが一般的のようです。
あ、半分の場合は「半分」「半切」と表現するスーパーさんもありますね。
あと、握り寿司の「1貫」=「2個」が正解なんですが、「え?1個じゃないの?」と思われた方もいらっしゃるのでは。
というのも、ずっと前にテレビの街頭アンケートを見てたら、「1貫」は何個ですか?の問いに「1個」と答える人が、意外と多かったんです。
何で間違って覚える人がいるんだろう?と思ってネットで調べたところ……。
番組にもあったように、「貫」はもともと個数ではなく大きさ(分量)を表す単位だったわけですが、ある時ネタの大きさを売りにする寿司屋さんが現れて、そこでは1個を「1貫」として出したため、それが誤って広がって、1個=「1貫」として出す店がどんどん増えたってことでした(^_^;
※お勧めリンク
みんなの知識【ちょっと便利帳】ものの数え方・助数詞
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「その他いろんな物の数え方」の解答
・ぶどう → 房(ふさ)
・花 → 輪(りん)
・明太子 → 腹(はら)
・イス → 脚(きゃく)
・テント → 張(はり)
・電車 → 両(りょう)
・プール → 面(めん)
・ピラミッド → 基(き)
・ヒラメ → 枚(まい)
・蝶 → 頭(とう)
・神様 → 柱(はしら)
・入れ歯 → 枚(まい)
※拙ブログ関連エントリー/「ビーバップ!ハイヒール」
・09/5/9付:日本人の習慣の由来 「ビーバップ!ハイヒール」より
・6/13付:京都裏ミステリー七不思議第2弾 「ビーバップ!ハイヒール」より
・10/3付:国旗に秘められた物語第2弾「ビーバップ!ハイヒール」より
・11/23付:京都の地名に潜むミステリー「ビーバップ!ハイヒール」より
・12/20付:日本人の習慣第2弾 年末年始編「ビーバップ!ハイヒール」より
・10/1/11付:城に隠された歴史ロマン「ビーバップ!ハイヒール」より
・10/5/3付:したたかに生きる小国たち 「ビーバップ!ハイヒール」より
・10/6/21付:世界が忘れない日本の物語「ビーバップ!ハイヒール」より
・10/10/9付:ノーベル賞をもらえなかった北里柴三郎「ビーバップ!ハイヒール」
※拙ブログ関連エントリー/ 「日本人」シリーズ
・【一覧】外国人から見た日本と日本人
・08/11/3付:「雷」工藤艦長の武士道精神とサー・フォールの報恩
・08/12/16付:「ATLAS日本」アメリカから見た現代日本
・09/3/21付:桜と日本人の感性
・09/5/23付:日本とトルコ 友好の歴史
・10/3/30付:江戸時代を見直そう(2)
・10/8/14付:国の行く末を案じ…【将兵万葉集】(5)戦争裁判の犠牲者-2
・11/1/4付:「たけしの教科書に載らない日本人の謎」仏教特集
★このブログが面白かったらクリックして下さい→
★ご面倒でなければこちらも→
 アニメ「めぐみ」配信中。
アニメ「めぐみ」配信中。英語・中国語・韓国語版もあります。ダウンロードはこちらから。コピーフリーです。世界に広めましょう!
「島根県の竹島英文ページを検索に引っ掛かり易くする作戦」もよろしく。
takeshima dokdo dokto tokdo tokto
________________________________________________
★コメント・トラックバックを下さる方へ
お手数ですが規約(11.1.4改訂)に一度目を通された上でお願いいたします。
なおトラックバックについては現在「言及リンクなしトラックバック」をはじく設定にさせていただいています。ご容赦下さい。
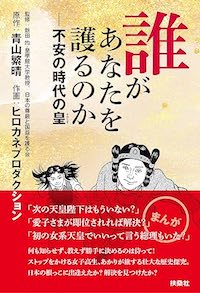
Comments
八百万の神の国である日本ならではだと思います。
家が神社です。「ちゅう」とも言いますが、厳密には「はしら」です。だからくっくりさん(この番組)が正しいです。
具体的には「ひとはしら・ふたはしら・みはしら・よはしら・いつはしら・むはしら・ななはしら・やはしら・きゅうはしら・じゅうはしら」です。
大きな動物の数え方が「匹」から「頭」になったのは英語の「ヘッド」からとなれば、
チョウチョも英語から来たのでしょうか。気になりますね。
>具体的には「ひとはしら・ふたはしら・みはしら・よはしら・いつはしら・むはしら・ななはしら・やはしら・きゅうはしら・じゅうはしら」です。
失礼ながら、「きゅうはしら」「じゅうはしら」ではなく、「ここのはしら」「とおはしら」では??
「きゅう」と「じゅう」からいきなり音読みになるように、いつからか決まったのでしょうか???
>「きゅう」と「じゅう」からいきなり音読みになるように、いつからか決まったのでしょうか???
ずっとそうなのか、途中から変わったのかはわかりませんが、知る限りでは「きゅう」「じゅう」です。
「きゅう」はわかりませんが、「とお」でなく「じゅう」なのは、「じゅうひとはしら」とつなげていくためではないかと思います。
>ずっとそうなのか、途中から変わったのかはわかりませんが、知る限りでは「きゅう」「じゅう」です。
「きゅう」はわかりませんが、「とお」でなく「じゅう」なのは、「じゅうひとはしら」とつなげていくためではないかと思います。
お答えをありがとうございました。
記紀等、古典では「十一柱」「十二柱」は、「とおあまりひとはしら」「とおあまりふたはしら」と読みますが、いつの時期にか変わったのでしょうね。
ありがとうございました。(^^)
「あまり(余り)」の「あ」が脱落して「とおまりひとはしら」「とおまりふたはしら」とも謂います。
蝶以外にも、カブトムシやクワガタも正式には「頭」で数えます。
英語での数え方である「one head, two heads」に由来するという説。
他の説に、昆虫標本は頭部がないと欠陥品となるために、
「頭」で数えたから・・・というのもあります。
いずれも、明治になって西欧から持ち込まれたものだと思います。
日本では人間より大きい動物・・・「頭」、
人間より小さい動物や昆虫など・・・「匹」
と、大きさの感覚でとらえているように思います。
それに比較すると、曖昧さがない西欧はいたって現実的ですね。
ちなみに動物園では鳥類を除く動物・昆虫は「頭」と数えるようです。
学術的な数え方と、生活の中での数え方があるのだと思います。
いずれにしても、日本語がゆたかな表現をもつということですね。
一般表現では「匹」φ(・_・)メモメモ
学術的に数えるか普通に数えるかで
変わるものがあるのですな。
尤もウサギの様に「羽」と「匹」
の二通りある動物も居ますが。
二兎追う者は一兎も獲ずって言いますよね? どうなんでしょう。
少し前に小学生の息子が同じことを言ってました。
その理屈だとイヌは一犬、ネコは一猫ってなっちゃうよね?って返しましたが・・・
助数詞は難しいですが、漢字の学習と同じく成り立ちを知れば少しは覚えやすくなるかも知れません。
皆「自動車」「電車」「トラック」「タクシー」と答えていきました。
私はちょっと生意気な子供だったので「自動車」も「トラック」も同じだろう等と考えていました。
挙手してもなかなか当たらずやっと自分の番になった時、自信満々に「テレビ」と答えると先生は「テレビは1台2台と数えるかしら?」と言いました。
子供にとって先生は絶対なので、私は皆にバカにされ笑いものにされました。
それまでは堂々と振舞えていたのに、以来人前に出ると赤面し緊張で声が震え話すことができなくなり、大人になった今も人前は苦手です。
30年以上経ちますが忘れられない嫌な思い出です。
友人に見える方がいて、その方が言うには、神社に大きな柱が天まで突き立っているのだそうです。
複数祀られている場合はその分柱があるとも。
関係ないことなんだけど、柱って数え方はそこから来るのかななんて思ったしだいです。
【車】→荷台を上から見た図。
:*:・( ̄∀ ̄)・:*樋口一葉良い名前だぁ〜(●´ω`●)ゞ(本当は違うんですけどねぇ)
☆日本には美しい音霊(おとだま)言霊(ことだま)があり、一斗二升五合→御商売益々繁盛ってユニークな洒落もあります。
☆英語でLOVEは【愛】だけですけど【恋】と言う意味もある日本(恋〜愛に変わる愛おしさを知っているから)
虫の鳴き声と云う叙情性の豊かさ、《貫》寿司の五色(赤青黄色緑黒)五味【甘・辛・酸・苦・旨み(こんぶ)】旨みがあるのは日本だけ&色彩の豊かさ七十五の季節感を持ち465色の色の名前、漢字を”感じ”五感が冴えますなぁ〜
☆神は人に宿らず、木&樹に宿る空氣の様な聖なる”氣”の存在ですから《御柱》と呼ぶのではないのでしょうか【桜】コノハナサクヤヒメとかね
☆『大切なものって、きっと目には見えないものなんだね』サンデク・ジュペリ〜星の王子様〜
※《知識は人との優劣を決めるモノではありません、【選択肢】が増える》って事ですから、人をバカにする奴が一番バカですよ。好奇心を失わず失敗を恐れず誰に遠慮など要りませんよ。
さて、いよいよ日本アジアカップ準決勝!【負けられない戦いがそこにある!】
о(ж>▽<)y ☆がんばれ侍JAPAN!